南 京 虐 殺(5−3)
―ティンパーリィ 『戦争とは何か』―
⇒「なかった派」の主張(1)
6 『戦争とは何か』について
ここで、東京裁判、南京裁判に多大な影響を与え、あるいは「30万人虐殺説」のルーツとも考えられるティンパーリィの『戦争とは何か』を紹介します。
『戦争とは何か―中国における日本軍の暴虐』(ハロルド・J・ティンパーリイ編著、WHAT WAR MEANS:The Japanese Terror in China)は「南京大虐殺」を世界に知らせた書物として有名です。
また、東京裁判では検察側の主要な証拠ともなりました。この書の内容、書かれた背景などを知ることによって、当時の米欧人の果たした役割が見えてきます。
オーストラリア人のティンパーリィは、南京戦当時、イギリスの新聞「マンチェスター・ガーデイアン」の中国特派員でした。また、この書の版元は左翼人の出版物を多く手がけたロンドンにあるゴランツ書店で、エドガー・スノーの『中国の赤い星』もここから発行されました。
書店主のビクター・ゴランツ自身も代表的な左翼知識人だったとのことです。
(1) 原著(英語)⇒中国語訳版⇒日本語訳版
発行は1938(昭和13)年7月、南京陥落の翌年と早く、原著(英語)とほぼ同時に中国語訳版『外人目睹中之日軍暴行』が出版されました。「目賭」は「目撃」の意です。フランス語版も出たとのこと。
 この中国語訳版(複数あり)は原著の英語版にない36枚の写真、もちろん残虐さを強調したもので、おなじみのものが数多く含まれています。左写真はそのうちの1枚です。また逆に記述が抜け落ちるなど、原著との差異が見られます。
この中国語訳版(複数あり)は原著の英語版にない36枚の写真、もちろん残虐さを強調したもので、おなじみのものが数多く含まれています。左写真はそのうちの1枚です。また逆に記述が抜け落ちるなど、原著との差異が見られます。
そしてこの中国語訳版から日本語に重訳され、前述の『外国人の見た日本軍の暴行』として出版されました。
 左写真はその復刻本(訳者不詳。評伝社、1982年)です。もっとも、日本語訳版も別にもう1種類あるのだそうです。
左写真はその復刻本(訳者不詳。評伝社、1982年)です。もっとも、日本語訳版も別にもう1種類あるのだそうです。
日本語訳『外国人の見た日本軍の暴行』は、もとになった中国語訳版とも異なる写真を、「原本中の写真は不鮮明のため削除し、新たに中国通信社提供による、当時の様子を伝える写真を掲載」したとして掲載しています。
しかし、明らかなニセ写真が含まれるなど、発行時の「日本軍たたき」の風潮下とはいえ、発行者の見識が問われる出来栄えとなりました。
(注) 原著からの邦訳文は、『日中戦争―南京大残虐事件2 英文資料編 』(洞富雄編、青木書店、1985)に収められていますが、この訳文について、「改ざん」とも言える誤訳があるとの指摘(『「南京事件」の探求』、北村稔、文春新書、2001年)がありますので、書き添えます。
(2) 概 要
この書の内容を知るために、日本語版の目次をご覧に入れましょう。
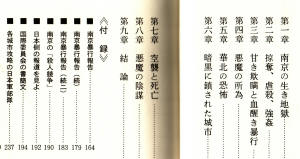
見ての通り、「本文」と「付録」とに大別できます。ほかに、ティンパーリィの書いた短い「序文」があります。
本文の第1章「南京の生き地獄」、第2章「掠奪、虐殺、強姦」、第4章の「悪魔の所為」などからも、この本の中身が日本軍の引き起こした「残酷物語」であろうことは一見して読み取れます。
目次だけでもうかがえる日本軍の残虐性ゆえに、この本のあたえた影響は国内外ともに大きく、国内にあっては「大虐殺派」のバイブルになったという話もあるくらいです。
ただ、本文はティンパーリィの書いたものだけでなく、匿名で書かれた第1章から第4章は、安全区国際委員会の委員でもあったベイツ・金陵大学教授とジョージ・フィッチ(南京YMCA副委員長)の2人によるものとわかっています。
例えば、第1章「南京の生き地獄」はベイツとフィッチ、第2章「掠奪、虐殺、強姦」はフィッチ、第3章「甘き欺瞞と血醒き暴行」はベイツといった具合です。
(注) 第3章の章題「甘き欺瞞と血醒き暴行」は、原著では「PROMISE AND PERFORMANCE」(約束と現実)となっています。
日本軍による殺害等、つまりベイツ教授の「非武装の4万人近い虐殺」、知人のドイツ人から聞いた「2万件強姦」、あるいは華中における「中国軍死傷者は少なくとも30万人、民間人死傷者もほぼ同数」などについては、すでに記したとおりです。
付録のうち、「南京暴行報告」(続、続2)と「国際委員会の書簡文」 がとくに重要です。この2つは、しばしば議論の対象となるのも、南京事件を考えるにあたっての重要な手がかり、判断材料を提供しているからです。
なお、「南京の『殺人競争』」とあるのは、例の「百人斬り競争」のことです。
(3) 「南京暴行報告」と「国際委員会の書簡」
「南京暴行報告」と「国際委員会の書簡文」は、徐 淑希・燕京大学教授が編纂した『南京安全区档案』に掲載されています。
「南京暴行報告」は国際委員会 (南京安全区国際委員会)が、日本兵による殺人、強姦などの犯罪行為を南京の日本大使館に抗議のために出したもので、第1件〜第444件 が知られています( 444件のうち39件欠 )。
また、「書簡文」は、国際委員会が日本大使館に送ったもので、69文書あります。
ティンパーリィは、『戦争とは何か』の刊行前にこの『南京安全区档案』の写しを入手し、選別のうえ全体の半分程度を収録しました。具体的には、暴行報告405件(444件マイナス39件)のうち160件程度、書簡文は34文書が収められています。
・ 南京暴行報告
いくつか例をあげますが、この報告は「日本軍南京占領の最初の2ヶ月に報告された話を完全に取り揃えている」(ティンパーリィ)といいますし、冒頭説明によれば、「以下、掲げる幾多の報告は中立の外国居留民の記録したものを日本当局に提出したもの」で、「この報告は難民区内の事件に限られている」とありますので、城内に設けられた「難民区内」に限定されることを考慮に入れる必要があるでしょう。
ただ、「難民区外」にいた住民となると限られた人数であるのはほぼ間違いない(異説あり)ところですから、「難民区内」がこうであったから、さぞ「難民区の外は・・」とはなりません。「難民区内」はほぼ「城内」に近いと言えます。
第 1件 12月15日・・道路掃除夫6名は鼓楼某家内で日本兵に銃殺され、1名は重傷を負った。
第12件 12月14日夜、11名の日本兵が銅銀巷の某家に闖入し、4名の女を輪姦した。
第15件 12月15日、日本兵が漢口路の某家に闖入し、嫁を強姦し、3名の女を拉致した。2人の夫は後をつけて叫んだが、銃殺に遭った。
第20件 12月16日夜、7名の日本兵が窓を破って入り難民から掠めた。校内の職員は与うべき時計もなく、提供する娘もなかったために傷つけられ、その場で婦女は強姦された。
第146件 12月23日午後3時、2名の日本兵が漢口路小学校収容所に闖入し、財物を捜索し、女子職員黄嬢を強姦した。我々は直ちに特別憲兵隊に報告した。憲兵が収容所に到着した時には、日本兵は一早く逃走していた。彼らは黄嬢を帯同して証人とした。夕方、また数名の日本兵が来て王夫人の女子を輪姦した。7時頃にはまた3名の日本兵が来て、2人の娘を強姦した。1人は僅かに13歳である。
なかには、「日本兵は紅卍字会の施術の鉄鍋1個を掠奪し、鍋の中の米粥を地上に投げた」(第24件)といったものも含まれていますが、ざっと目を通してゆくと、上のような強姦の類が目につくものの、殺害例はわずか しか見当たりません。
では、405件の報告例のうち、殺害事件や強姦事件などが一体、何件(何人)起こったのか誰でも知りたくなるでしょう。
何人かの研究者が数えていますが、殺人は「50人程度」としています。各人、多少の違いはあるもののその差は小さいものです(詳しくは ⇒ 6−1)。
となりますと、話は実におかしなことになります。ベイツは城 内で「1万2千人の男女および子供が殺された」と東京裁判法廷で証言、この証言が判決に直結したのですから。
念のために、判決文をもう一度、見ておくことにします。
〈兵隊は個々にまたは2、3人の小さい集団で、全市内を歩きまわり、殺人・強姦・掠奪・放火を行った。そこには何の規律もなかった。多くの兵は酔っていた。
それらしい挑発も口実もないのに、中国人の男女子供を無差別に殺しながら、兵は街を歩きまわり、・・。これらの無差別の殺人によって日本側が市を占領した最初の2、3日の間に、少なくとも1万2千人の非戦闘員である中国人男女子供が死亡した。〉
この2つの極端ともいえる相違、説明がつけられるでしょうか。無理だと私は思いますが。
それに、紅卍字会による城内の埋葬数は全期間を通して1,793体という統計もあることですし。
暴行報告の統計の細部は別項(6−1)で取り上げますが、このように「殺害数」の少ない点もさることながら、個々の報告例に不自然さがあって、にわかに信じられないなど、疑問点が多く存在します。
とくに、殺害事件の少なさは、逆に「南京暴行報告」が「大虐殺」を否定しているという見方が出てくるのももっともなことと思います。
・ 書 簡
一方の書簡ですが、第1号文書〜第34号文書がこの書に収められています。
この中に、市民のほとんどが避難した「難民区」の人口は「20万人」(12月17日付け第6号文書ほか)と記しています。
この人口が大虐殺のために、さぞ急減したのかというと、ほぼ1ヵ月後の第19号文書(1938年1月14日付け)に「25〜30万人」、第22号文書(1月17日付け)には「25万人」とあるなど、逆に人口増となっています。
このことと「南京暴行報告」の殺害例の少なさと合わせ考えますと、ベイツ教授の報告と東京裁判の判決を根っこから否定してしまうことにもつながってきます。
もちろん、「暴行報告」も「書簡」も、「城 外」での出来事は含まれていませんから、あくまで「城 内」にかぎった話ですが。
7 周到に用意されたプロパガンダ
となりますと、『戦争とは何か』の記述の信頼性をどう考えたらよいのでしょうか。オーストラリア人である編著者・ティンパーリィ、あるいはベイツ教授らが政治的に中立な第3者の記録と考えられそうですが、まったく違うことが判明しています。
 国民党政府がティンパーリイ(中国名・田 伯烈)をアメリカやイギリスに派遣、宣伝工作に当らせたこと、次いで「中央宣伝部顧問」に任命したことを、鈴木 明が『 新「南京大虐殺」のまぼろし』(飛鳥新社、1999)のなかではじめて指摘しました。
国民党政府がティンパーリイ(中国名・田 伯烈)をアメリカやイギリスに派遣、宣伝工作に当らせたこと、次いで「中央宣伝部顧問」に任命したことを、鈴木 明が『 新「南京大虐殺」のまぼろし』(飛鳥新社、1999)のなかではじめて指摘しました。
その後、北村 稔・立命館大学教授による『曾虚白自伝』の発見、東中野 修道・亜細亜大学教授による「極機密」の印が押された『中央宣伝部国際宣伝処工作概要』(以下、『工作概要』) の発掘などによって、国民党政府の日本に対する「対敵宣伝」の全貌がかなりハッキリしました。

 左写真は北村教授の著作『「南京事件」の探求』(文春新書、2001)と東中野教授の『南京事件 国民党極秘文書から読み解く』(草思社、2006年)で、発見、発掘した資料について詳しく書いてあります。
左写真は北村教授の著作『「南京事件」の探求』(文春新書、2001)と東中野教授の『南京事件 国民党極秘文書から読み解く』(草思社、2006年)で、発見、発掘した資料について詳しく書いてあります。
これによって、国民党政府の対敵宣伝、つまり日本向けのプロパガンダが組織的に計画されたこと、また、ティンパーリィだけでなく、南京の戦争被害を調査したスマイス教授もまた、中央宣伝部と強いかかわりがあったことなどが明らかになりました。また、ベイツ教授も中華民国政府顧問であったことも判明しています。
(1) 対敵宣伝機関⇒「中央宣伝部国際宣伝処」
以下、必要と思われる事項を要約します。
南京陥落約1ヵ月前の1937(昭和12)年11月、国民党は中央宣伝部を設立、下部機構に対外宣伝を目的にする「国際宣伝処」を設けました。この国際宣伝処は蒋介石に直属し、重慶を本部に上海、香港等に支部を、ニューヨーク、ワシントン、ロンドンほかに事務所を置きます。
国際宣伝処の長は5科3室を有し、うち1科が「対敵宣伝科」でした。対敵宣伝科の工作活動は1937年12月1日に開始されたこと、また対敵宣伝本として田 伯烈(ティンパーリィ) が書いた『外人目賭之内日軍暴行』を国際宣伝処が「編集印刷」したことなどが、『工作概要』に記されています。『外人目賭之内日軍暴行』は『戦争とは何か』そのものです。
国際宣伝処の長は曾 虚白という人物で、金陵女子大学教授という経歴を持ち、戦後、台湾にわたり中央通信社社長になるなどの履歴を有しています。
(2) 金で動いた代弁者たち
台北で発行された『曾虚白自伝』(聯経出版社、1988年)に書かれた記述から、『戦争とは何か』の素性がハッキリと読み取れます。また、次項の『スマイス報告』もまた、宣伝処の影響下にあることもわかります。
以下、『「南京事件」の探求』から引用します。
〈ティンパーリーは都合のよいことに、我々が上海で抗日国際宣伝を展開していた時に、
上海の「抗戦委員会」に参加した3人の重要人物のうちの1人であった。オーストラリア人である。
・・そして彼に香港から飛行機で漢口(南京陥落直後の国民政府所在地)に来てもらい、直接に会って全てを相談した。
我々は秘密裏に長時間の協議を行い、国際宣伝処の初期の海外宣伝網計画を決定した。
我々は目下の国際宣伝においては中国人は絶対に顔をだすべきではなく、
我々の抗戦の真相と政策を理解する国際友人を捜して我々の代弁者になってもらわねばならないと決定した。
ティンパーリーは理想的人選であった。かくして我々は手始めに、
金を使ってティンパーリー本人とティンパーリー経由でスマイスに依頼して、
日本軍の南京大虐殺の目撃記録として2冊の本を書いてもらい、印刷して発行することを決定した。(中略)
このあとティンパーリィはそのとおりにやり、(中略)2つの書物は売れ行きのよい書物となり宣伝の目的を達した。〉
2冊の本というのは、『日軍暴行記実』と『南京戦禍写真』で、前者は『戦争とは何か』、後者は『スマイス報告』のことを指します。また、曾虚白は「南京大虐殺」という用語を使っていますが、この本の発行が1988年だったからに違いなく、当時の記録ならばまず使わなかった表現と思います。
このように、自らは顔を出すことなく国民党政府の目的を達成するため、ティンパーリィという理想的な「代弁者」を得て、「金を使って」2冊の本を書かせました。ですから、『戦争とは何か』と中国語訳版の『外人目賭中之日軍暴行』が同時に出版されたのも当然のことでした。
この書を出すにあたって、ティンパーリィとベイツの往復書簡が残っています。ティンパーリィは次のように書きました。
「この本はショッキングな本とならなければなりません。
もっと学術的取り扱いをすることによって、ある種のバランス感覚もできるでしょうが、
ここでは劇的な効果をあげるためにもそれを犠牲にしなければならないと思います。」
これほど『戦争とは何か』の性格をあからさまに示した手紙もまれでしょうし、あれこれつけ加える必要がないくらいと思います。
日中戦争に対して、アメリカは表向き中立の立場をとっていました。日米開戦がちょうど4年後の1941(昭和16)年12月であってみれば、このときも、日米関係がギクシャクしていたであろうことは容易に想像がつきます。
南京に居住している米欧人から見れば、迫まりくる日本軍に対して悪感情を持ち、中国人に肩入れするのもごく自然のことでしょう。とくに、「安全区」設置に尽力したアメリカ人の多くが、布教を目的とする宣教師であってみれば、この傾向は一層、強くなっておかしくありません。ですが、それだけではなかったわけです。
(3) 日本の代弁者たち
ティンパーリィ(党中央宣伝処顧問)、ベイツ(国民政府顧問)に加え、さらにスマイスを加えた3人の行為は、国民党政府の金を伴った要請で行われ、その成果である『戦争とは何か』は中立の立場で書かれた記録にほど遠く、また『スマイス報告』も真っ白でなく何らかのバイアスがかかっているという疑いがでてきます。
また、「宣伝の目的を達した」とする曾虚白(国際宣伝処処長)の自己評価ももっともなことで、日本の大虐殺派のバイブルとなり、今日なお「20万人以上」などとする日本の歴史教科書の存在、中国にまったく頭の上がらない日本と日本人の現状を見れば、当初の「宣伝の目的」をはるかに超えた永続的成果をあげつづけているといって差し支えないでしょう。
ただ、永続的成果を挙げるに至ったのも、戦後4半世紀過ぎて、中国の「理想的な代弁者」が日本から出てきたことと無縁ではありません。
先陣を切ったの「中国の旅」を連載した朝日新聞社、裏づけ抜きの記事を書き連ねた本多勝一記者でした。本多の南京大虐殺記念館からの表彰(2007年)も、ベイツ教授が国民政府から受けた表彰とどこやら軌を一にしているようにも思います。
さらには、遅れをとっては大変とばかりに、後につづいたのは毎日、NHK、地方紙など報道機関、歴史専攻の大学教授、文化人らでした。
彼らはせっせと中国のいうがままに、公正を装って「南京大虐殺30万」の正当性を補強したばかりか、日本軍の悪行と聞くや、これまた裏づけのないいままに大見出しで報じ、お涙頂戴の感情を表面に立てた番組で「虚偽を事実」とあおり立てました。
こうして日本と日本人を貶め、NHKもまたこの線に沿った番組作りに拍車をかけたのです。
⇒ 「なかった派」の主張(1)
⇒ 総目次へ ⇒ トップ頁へ
 この中国語訳版(複数あり)は原著の英語版にない36枚の写真、もちろん残虐さを強調したもので、おなじみのものが数多く含まれています。左写真はそのうちの1枚です。また逆に記述が抜け落ちるなど、原著との差異が見られます。
この中国語訳版(複数あり)は原著の英語版にない36枚の写真、もちろん残虐さを強調したもので、おなじみのものが数多く含まれています。左写真はそのうちの1枚です。また逆に記述が抜け落ちるなど、原著との差異が見られます。 左写真はその復刻本(訳者不詳。評伝社、1982年)です。もっとも、日本語訳版も別にもう1種類あるのだそうです。
左写真はその復刻本(訳者不詳。評伝社、1982年)です。もっとも、日本語訳版も別にもう1種類あるのだそうです。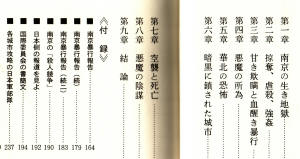
 国民党政府がティンパーリイ(中国名・田 伯烈)をアメリカやイギリスに派遣、宣伝工作に当らせたこと、次いで
国民党政府がティンパーリイ(中国名・田 伯烈)をアメリカやイギリスに派遣、宣伝工作に当らせたこと、次いで
 左写真は北村教授の著作『「南京事件」の探求』(文春新書、2001)と東中野教授の『南京事件 国民党極秘文書から読み解く』(草思社、2006年)で、発見、発掘した資料について詳しく書いてあります。
左写真は北村教授の著作『「南京事件」の探求』(文春新書、2001)と東中野教授の『南京事件 国民党極秘文書から読み解く』(草思社、2006年)で、発見、発掘した資料について詳しく書いてあります。